持続可能な社会を構築するための取り組みのひとつに、建築分野における木の利活用があります。海外では木造の高層ビルも登場するなど、この分野の技術の進展には目をみはるものがあるのですが、その実現に大きな貢献を果たしているもののひとつに、木の最大の弱点である耐火性能を向上させた新しい木質耐火部材の開発があります。清水建設もこのニーズに対応し、スリム耐火ウッドという製品を送り出しています。今回はこの開発に携わった3人の技術者に話をお聞きしました。

火災に強いだけでなく薄く、軽く
木材といえば、長らく日本の建築においてはメインの建材でした。むしろそれ以外の選択肢はなかったともいえます。ところが大震災や戦災による市街地火災でその弱点である燃えやすさがクローズアップされるようになり、建築の構造体については鉄骨やコンクリートなどがとって代わるようになっていきました。この流れが変わったのが2000年の建築基準法改正。燃えやすいという弱点を克服できるのであれば、木造でも大規模建築物が造れるようになったのです。これを満たす手段のひとつが木質耐火部材です。スリム耐火ウッドをごく簡単に紹介するなら、荷重を支える木材を芯として、その周囲を耐火性能に優れた材料で被覆し、さらに化粧材を巻いた木質耐火部材ということになります。開発を主導した水落は次のように振り返ります。

「開発がスタートしたのは2013年のことです。木質耐火部材にはいくつかのタイプがある中、表面に木目が見えたり触れたりできるほうがいいだろうと考え、木材現しにして被覆材により耐火性能を確保する燃え止まり型にすることは、初期の段階に決めました。被覆材をできるだけ薄く軽くということも開発要件にしていました」(水落)
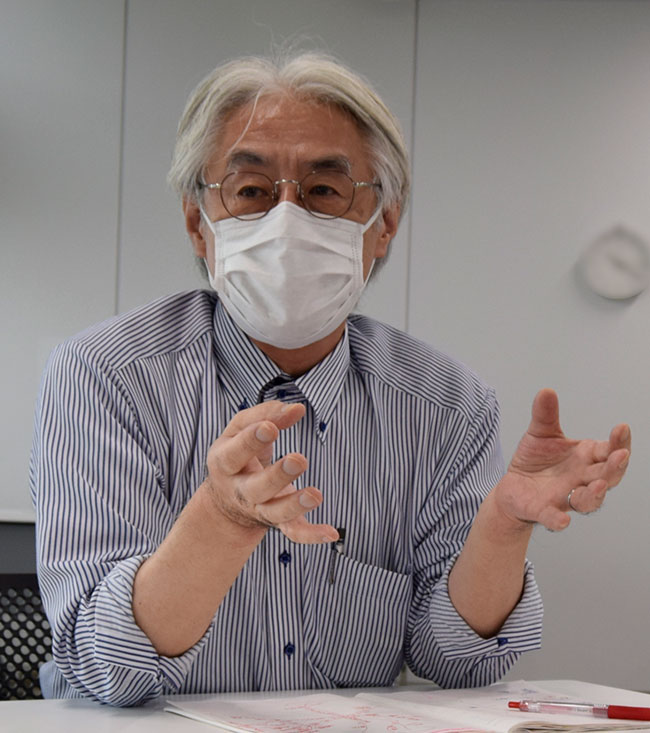
最初は難燃木材をはじめ、さまざまな素材を試したと話すのは、技術研究所の広田です。
「被覆材を厚くすれば性能確保は簡単です。薄く軽くというところが、スリム耐火ウッドの独自性であり、苦労したところですね」(広田)

当時、技術研究所に所属し、広田とともに開発に従事していた井戸も次のように話します。
「様々な被覆材を用いた小規模試験体で実験を実施していく中で、複数の被覆材の組み合わせを採用しました」(井戸)
異種材の組み合わせで性能を確保
実験で有力だったのが、強化石膏ボードに、広田が以前より取り組んでいた加熱により発泡する耐火シートを組み合わせたペアリングでした。
「シートなど耐火部材の適用性に関する検討は、それ以前から取り組んでいたのです。耐火シートは厚さ約2mmと文字どおりのシートなのですが、加熱して250度程度に達すると、発泡しておよそ20倍に膨張します。これが断熱に大きく貢献します」(広田)

こうして基本コンセプトが固まったスリム耐火ウッド。性能評価機関の性能評価試験を通じ、確かな耐火性能を持つことが実証されるに至りました。2015年に1時間耐火木質柱としての大臣認定を取得。翌年には1時間耐火木質梁としても大臣認定を取得し、耐火木造建築の可能性を大きく拡げる部材として完成を見たのです。
「二重の燃え止まり層で性能を確保しつつ、薄く、軽くということもクリアできました。芯材はもちろん、化粧材にもスギやカラマツ、ヒノキなど、いろいろな材が使えるため、意匠設計の自由度が高いうえ、不燃木材を使うことで内装制限の法令規制にも対応可能です。また、従来の認定品と比較すると被覆層の厚みは最大で5割ほど薄くなっており、最もスリムな木質耐火部材となっています」と水落が紹介するように、耐火構造部材として優れた性能を備えた製品に仕上がりました。しかし、思わぬところで逆風にさらされることになります。

逆風からフォローの風に吹かれて
それは、まだ市場では建築物への木材利用のニーズがそれほど高まっていなかったということでした。
「鉄骨やコンクリートは汎用技術としてローコスト化が追求されていたのに対し、耐火木造建築はコストが高くなってしまうことが大きな課題でした」と水落が話せば、井戸も「せっかく開発したものがなかなか案件として採用されない。これは精神的に辛いところでした」と苦笑いを浮かべます。
そんな風向きが変わったのは数年前のこと。この頃から世界的に環境意識が高まり、省エネと木材の利活用が脚光を浴びるようになってきたのです。
| 法制度の動き | 法制度改正による変更点など | |
|---|---|---|
| 2000年 | 建築基準法の性能規定化 | 大規模な木造建築が可能 |
| 2010年 | 公共建築物等の木材利用促進法 | ※林業再生が主目的 |
| 2015年~2020年 | 建築基準法の改正 SDGsの採択 カーボンニュートラルへの宣言 |
・3階建て学校、3000m2超えの木造が可能に ・建物高さ制限13m→16mに緩和など |
「高校時代に家の近所で大きな火事があったこともあり、大学で火災安全工学を学び、入社後はずっとスリム耐火ウッドの開発に携わってきました」と話す井戸。
「2003年に建築学会で『火災に強い高層木造建築』の設計コンペがありました。実は水落さんや私もそのプロジェクトに加わってコンペに参加し、最優秀賞を受賞しました。当時考えられるさまざまな技術を盛り込んだ革新的なプランでした」と開発前夜の秘話を明かした広田。
「私は自然が好きで、木をずっと身近に感じていました。入社後は防火関連の仕事をしていましたが、将来的に木の構造物が増えてくるだろうと直感してから木もテーマにするようになりました。今後もこの技術を拡張し、森林保全まで視野に入れた『木の循環』をベースに、安全・安心な木造建築を広めていきたいですね」と未来図を描く水落。
スリム耐火ウッドは清水建設の社宅「アネシス茶屋ヶ坂(名古屋市)」に初めて採用され、2020年に竣工しています。それ以降、問い合わせは増えているとのこと。持続可能な社会のために、スリム耐火ウッドが本領を発揮するのは、まさにこれからなのです。


